こんにちは。ティーダです。
今回は2021年5月26日に公開されたアステラス製薬の経営計画2021 (2021~2025年度) について、最新情報と個人的な見解も含めて解説していきます!
今回の説明会では、2027年頃に迎える「XTANDIのパテントクリフ」を乗り越える戦略について特に強調されていました。
この記事を読むことで、今後のアステラス製薬の戦略と将来性を理解する助けになります!
当記事では特に、2030年以降の成長に繋がるFocus Aria アプローチや創薬プラットフォームについて、研究者の目線から考察していこうと思います!
経営計画2021の概要
アステラス製薬は、2015年にたてた成長計画の中で
変化する医療の最先端に立ち
科学の進歩を患者さんの「価値」に変える
という2030年にありたいビジョンを掲げています。
この2030年ビジョンを実現するための第二次中計として今回の経営計画2021は設定されています。
市場からの突き付けられている3つ課題
アステラス製薬は現在市場 (投資家など) から以下の3つの課題について解決を求められていると認識しています。
- XTANDIのパテントクリフを埋められる製品があるのか?
- Focus Areaアプローチから価値あるパイプラインは生まれるのか?
- 販管費の削減は十分なのか?
今回の経営計画2021では特に上記の3つの課題について解決策を提示するような形で話が進められています。
具体的な目標設定
具体的に今回の中計では以下の「戦略目標」が掲げられています。
- 患者さんのより良いアウトカムの実現
- 科学の進歩を確かな「価値」へ
- Rx+ ビジネスの進展
- サステナビリティ向上の取り組みを強化
上記の戦略目標を達成することで以下の「成果目標」を達成することを計画しています。
- 売上収益: XTANDIおよび重点戦略製品の売上は2025年度に1.2兆円以上
- パイプライン価値: Focus Areaプロジェクトからの売上は2030年度に5,000億円以上
- コア営業利益率: 2025年度に30%以上
つまり、アステラス製薬は以下のような公算でXTANDIのパテントクリフを乗り越えることを考えています。
XTANDIのパテントクリフによる減収分7000億円を
①Foucs Areaプロジェクトからの製品売上5000億円と、②重点製品成長2000億円でカバー!!
上記の成果目標を達成することで、2025年時点で時価総額7兆円以上の価値を市場から評価してもらえると考えています。
(2022年2月現在で、国内製薬の時価総額ランキングは、
第1位:中外製薬 6.2兆円、第2位:武田 5.2兆円、第3位:第一三共 5兆円、第4位:アステラス 3.6兆円)
XTANDIおよび重点戦略製品:2025年度に1.2兆円以上
まず2020年代に以下の複数の重点戦略製品について大きな成長を見込んでいます。

それぞれの製品売上高を合計したときに、2025年頃に1.2兆円以上の売上高を想定しています
AT132 (X連鎖性ミオチュブラーミオパチー) については被験者が死亡したことにより開発は中止されています。
AT132以外の製品の開発は想定通り進捗しています (2022年2月現在)
2025年時点で、全社的な売上高は1.8兆円以上を計画しています。
XTANDIのパテントクリフが2027年頃に起こった後にも、2030年には他の重点戦略製品とPrimary Focusからの製品の収益によって、同程度の全体売上高をキープできると考えています。
Primary Focusから後期開発品を創出し、2030年度に5,000億円以上
現在アステラス製薬は研究方針として、Focus Areaアプローチという方法をとっています。
アステラスが2018年頃から打ち出した新たな研究開発戦略のことです。
以下で示す3つの構成要素 (バイオロジー、モダリティ、疾患) を組み合わせて定義付けられる集合をFocus Areaとして定義し、このFocus Areaに独自のプラットフォームを構築することで革新的な創薬を目指す戦略です。
- バイオロジーの究明:
疾患の原因解明が進み、創薬ターゲットとして適切な標的因子にアプローチする - モダリティ/テクノロジーの活用:
標的因子にアプローチするための最適な治療手段を選択する。そのための革新的な技術を獲得し、汎用性のあるプラットフォームとして構築する。 - 患者ニーズの充足:
最先端の化学を活用して、バイオロジーとモダリティ/テクノロジーの独自の組み合わせを見出し、開発実行性やマーケットアクセスなどの課題を克服しながらアンメットニーズの高い疾患に応用する。

既にPrimary Focus領域 (最初の4つの注力領域) では、複数の開発品が創製されています。
- 再生と視力の維持・回復
- ミトコンドリアバイオロジー
- 遺伝子治療
- がん免疫
詳しくはアステラス製薬のHPでも紹介されています。
この中計発表時点では、Primary Focus領域の開発候補品は2025年度までにPoCを見極める製品が31品目存在しました。
これらの製品が2030年度には5000億円以上を売り上げることで、XTANDIのクリフを乗り越える計画です。
2022年2月時点で1製品 (ASP1948) が中止になり、2製品の開発が遅延しています。
さらに、Focus Areaアプローチの強みとして、あるプラットフォームのリード化合物でPoCを一つで獲得できれば、同じプラットフォームにおける後続プロジェクトの達成確率を上げることが可能です。
重要技術基盤の活用・発展
現在のPrimary Focus領域を支える研究基盤についても紹介されています。
細胞医療プラットフォーム
細胞医薬は複数のPrimary Focusに使用されている重要なプラットフォーム技術です。
2021年5月で11種類の細胞について分化プロトコールの確立が完了しています。
2025年には20種類以上で分化プロトコールの確立を計画しています。
特に期待しているのは、ユニバーサルドナー細胞による他家細胞の移植によるがん免疫プロジェクトです (ザイフォス社由来)。
2022~2023年度に臨床入りを計画しています。
また、全ての治験薬は2020年度から稼働しているアメリカの自社製造工場にて製造可能です。
AAV技術の活用:遺伝子治療および細胞医療プラットフォーム
さらに複数のPrimary Focusで活用されているAAV技術についても紹介されています。
AAV技術自体は2020年に買収したオーデンテス社により得た技術です。
遺伝子治療と細胞医療に対して、2つのプラットフォームで有機的に活用されています。
また、GMP製造に関しても自社でまかなえるプラント2つも持っています。
AAV技術は遺伝子治療と細胞医療をつなぐ技術で、それぞれを同時に保有することがアステラスの大きな強みであると考えています。
2021年12月2日には、骨格筋・心筋を対象としてAAVベクターの共同研究でアメリカのDyno Therapeutics社と提携を発表しました。
Dyno Therapeutics社は、機械学習を応用して細胞送達に関わるAAVの外殻タンパク質(カプシド)を最適化する技術を持っています。
その他の技術的な提携
- 2021年7月30日、イスラエルのMinovia Therapeutics社と、ミトコンドリア機能不全に起因する疾患に対する細胞医療研究について、戦略的提携を結んだと発表した。
Minovia社の独自技術を使い、健康なミトコンドリアを患者の体内に運び、組織を修復することで、ミトコンドリア機能不全に起因する疾患の治療を目指す。 - 2021年11月15日、mRNAを使った再生医療プログラムの創出を目指し、Pantherna社と契約を結んだと発表した。
Pantherna社のmRNA技術プラットフォームを活かし、再生医療分野での治療応用を目指す。 - 2021年10月1日、順天堂大学院医学研究科に「ダイレクトリプログラミング再生医療学講座」を開設したと発表した。
講座では、K因子を用いたダイレクトリプログラミングにより、1型糖尿病などに効果がある新規モダリティの創製を目指す。
Rx+:2025年度までに収支トントンの結果を達成
Rx+事業は、医療用医薬品の枠を超えた新規事業の創出を目指しているプロジェクトです。
2018年から本格的に立ち上がった本プロジェクトは、今中計の期間内には事業化のフェーズに入ることを計画しています。
保険償還を目指さない「デジタルヘルスサービス」について、2025年度までに5つ以上のプロジェクトを事業化予定しています。
- マイホルターⅡ:
心電計データをAI(人工知能)で解析する - Fit-eNce:
科学的根拠に基づくフィットネスサービス
etc…
保険償還を目指す「デジタルセラピューティクス」も2025年度までに複数の事業化を計画しています。
- Blue Star:
2型糖尿病に対する処方アプリ
etc…
他にも複数のプロジェクトが開発中であり、特に外部連携を通じて取り入れた製品について中計期間中に事業化が予定されています。
- ASP5354:
腹部や骨盤内を手術する際、尿管を光らせて可視化する蛍光造影剤 (FDAファストトラック指定) - セラノスティックス:
患者の病変の位置や状態を診断し、それぞれに適した治療かどうかを判定しながら行う治療法に関するプロジェクト - 埋め込み型医療機器 (アイオタ社):
電気刺激による疾患の治療・制御等を目指して開発中
etc…
Rx+全体では、2025年度までに収支がトントンになることを計画しています。
さらに、2030年までには、200~500億円の収益を期待し、それ以降はアステラスの屋台骨の1つとなることを目指しています。
機関投資家のQ&A
Q:2018年頃に一度算出されていたfezolinetantの予想売上高が上方修正された理由は?
A:Ph3試験の結果から、Ph2bで考えられていた安全性懸念が払拭されたため、投与患者層が拡大したから。
さらに、患者への啓発活動についての戦略がブラッシュアップされることで、市場性が以前より高められる見通しが立ったから。
Q:2025年時点で時価総額7兆円になる根拠はなにか?どういった計算で7兆円が出たのか?
A:複数の計算方法で算出した結果である。「現状利益」と「将来の成長性」をそれぞれ1.5倍することで、トータルで時価総額が2.25倍になると単純には考えている。
他社の時価総額を明確に意識したわけではない。
Q:Primary Focus領域の5000億円以上という算出の根拠は?それぞれのポテンシャルや成功確率はどのように考えられているのか?
A:2025年までにPoCを見極める31品目それぞれに対して、「成功確率」と「予想売上高」をかけて積算した数値である。CEOが一番期待しているのは、がん免疫領域の人工アジュバントベクター細胞と腫瘍溶解性ウイルス。
具体的には、31品目のうちでモンテカルロシミュレーションを実施した。その結果、3000億から7000億円程度の間に落ち着くというのが今の見立て。
個人的な見解
XTANDIクリフを乗り越えられる公算は現時点で確度が低い?
今中計で、最も注目されているのはXTANDIクリフによる売上高減少を本当にカバーできるのかという点です。
しかし、今回の計画で発表されていたPrimary Focus領域が5000億円以上を達成するという試算について、その予想売上高の根拠は全く示されていません。
PoCを見極める開発品が31品目あることは確かですが、その中で本当に売上に貢献できるだけ本気の品目はいくつあるのでしょうか?
個人的には、XTANDIクリフを乗り越えられる分だけの金額をとりあえず提示しているように感じました。
(投資家の質問でも同様の見方があったのではないでしょうか??)
今後の開発の進捗次第ですが、現時点ではクリフを乗り越えられる公算はまだない気がします。。。。
外部から後期開発品を導入することになるのでしょうか??
販管費の削減について非常に強調している
今回の計画を聞いていて、ここまで販管費の削減を意識している会社は珍しいように感じました。
実際に2022年現時点で営業部署の人員削減に注力しています。
グローバルで1000人の削減を実施しています。
今後は研究所等の他部署に対しても不要人材の削減が拡大していくことが想定されます。
おそらく、この動きはパテントクリフを乗り越えられなかった場合の傷を小さくするためにも実施していると思います。
同様にクリフを迎える大日本住友や塩野義でも同様の動きは今後活発化することが予想されますね。
最後に
今回はアステラス製薬の経営計画2021についてまとめてきました。
個人的にはまだXTANDIクリフを乗り越えられる公算は確度が低いように感じました。
後期開発品による売上高が保証されない限り、時価総額などの今回立てた目標は全て達成できないと思います。
今後の開発品の進捗に期待ですね!
また、近日中にR&Dミーティングが開催されるので、それについてもまとめ記事を書いていきたいと思っています。
R&D ミーティング
2022年3月9日(水) 9:30-11:00
-遺伝子治療への取り組み-
最後まで読んで頂きありがとうございました!


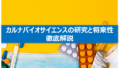
コメント